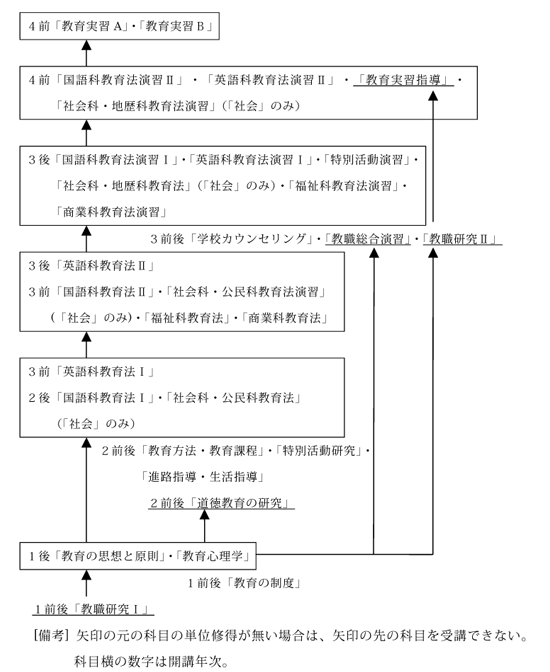第3節 総合文化学部
(1) 教育研究の内容等
【現 状】
①教育課程
ア、学部における教育課程の基本的考え方
本学部は、「人間と文化に対する深い洞察と知識を求める」という理念のもとに、①情報教育の重視、②外国語教育の重視、③ボランティア教育の重視、④地域教育の重視、⑤問題解決型人材育成の重視の5項目を教育目標に掲げている。その教育目標を実現するために、授業科目を共通科目と専門科目に大別し、大学設置基準第19条「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」ことを目的とした共通科目は全学共通で運営し、学校教育法第52条「深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力」を培うことを主な目的とした専門科目は学科ごとに体系的に配置している。
一般教養的な授業科目として「人間・文化」「社会・生活」「自然・環境」「情報科学」「国際理解」「健康・スポーツ」「沖縄関係」「テーマ」「外国語」の9科目群を全学の共通科目として設定し、社会・文化・自然の幅広い教養に加えて、情報及び国際という現代的な課題に対応する能力の涵養と沖縄・平和という地域的な課題への思索を加え、総合的な判断力の養成を目指している。本学の共通科目の理念・目標としては、①普遍的人間形成、②研究能力の開発、③社会人としての教養形成である。8科目群の履修方法については、学生の学習主体性を重視する意味で科目選択は自由を原則としているが、特定の科目群に偏った履修は、幅広い教養の育成という共通科目の目標に反するので、外国語科目群を除いて3つ以上の科目群から科目を履修するように指導している。
本学部では、英語・独語・仏語・スペイン語・中国語・韓国語の外国語科目群から8単位あるいは12単位を必修としている。本学部では、学生個々人の興味に従った多様な文化の理解を教育目標の一つにしているので、第一外国語、第二外国語という区別はしていない。したがって、外国語科目の履修方法は、それぞれの学科の教育目標によって異なっており、それが学科による教育の特徴であり、本学部の特徴となっている。日本文化学科は、広く文化に興味をもってもらうために、英語を第一外国語の必修とするのではなく、6外国語の中から各自の興味にあった外国語の中から8単位を履修することになっている。英米言語文化学科は、英語に偏らずに他の言語をも学習して英語や日本語との比較の視点を養うために、英語を必修とせず、全ての外国語の中から自由に選択することができる。社会文化学科は、世界共通語としての英語を基本とすることから4単位は英語を必修とし、残りの8単位は英語も含めて自由に選択できる。多くの文化の理解を促すために、英語以外の外国語の修得を推奨している。また、その分外国語の履修単位数を多く設定している。人間福祉学科も、4単位の英語学習を必修とし、残りの4単位は英語を含めて6外国語から自由に選択できる。
共通科目は、全学的に運営しているため、各科目群責任者及び各学科長から構成される共通科目運営委員会によって実施、運営され、その委員長は教務部長が務める。
教育課程における基礎教育は、大学での学習を発展させる重要な科目として、共通科目だけではなく、専門科目にも主に1年次の科目として配置されている。本学部では、すべての学科において1年次に必修の演習を設置し、大学における学習方法、学科内容の理解、文章表現の方法などについて少人数で学ぶことになっている。それ以外に、情報関係の基礎教育として、日本文化学科では「人文情報基礎」、英米言語文化学科では「情報基礎Ⅰ・Ⅱ」を必修科目として置いている。その他、各学科における学習の基礎的かつ入門的な科目として、1年次の必修科目を配置している。日本文化学科では「日本文化論」「琉球文化論」、英米言語文化学科では「英文法Ⅰ」「英作文Ⅰ」「英語講読Ⅰ」「オーラルコミュニケーションⅠ」、社会文化学科では「社会学概論」「文化人類学概論」「平和学概論」「環境思想論」「ジェンダーの思想」、人間福祉学科では「社会福祉原論」「社会学概論」「心理学概論」である。
共通科目と専門科目の各学科における単位数は、下表のとおりである。
|
区 分 |
日本文化 |
英米言語文化 |
社会文化 |
人間福祉 |
|
共通科目
|
外国語 |
8 |
8 |
12 |
8 |
その他の共通科目 |
20 |
20 |
20 |
20 |
小 計 |
28 |
28 |
32 |
28 |
専 門 科 目
|
68 |
76 |
72 |
76 |
自 由 選 択
|
28 |
20 |
20 |
20 |
|
合 計 |
124 |
124 |
124 |
124 |
本学、本学部の全体的な教育課程の特徴は、自由選択の制度である。自由選択とは科目の区分ではなく、学生の学習目的にそって各自が多様な教育課程を編成する点にある。つまり、共通科目と専門科目の必要最低単位数を卒業単位数より少なく設定し、その差を自由選択として共通科目及び専門科目から組み合わせて卒業単位を埋めていくという履修上のシステムである。他学部、他学科科目や他大学履修科目も自由選択に加えることができ、履修上の「フリーゾーン」としての性格をもつ。共通科目を多く履修するか、専門科目を多く履修するか、自由選択の単位数をどのように埋めるのかは各学生の学習目的に基づく自主性に任されており、学生ごとに多様で個性的なカリキュラムを組み立てることができる。つまり、大学から与えられたカリキュラムと履修方法に縛られるのではなく、学生が、与えられたカリキュラムの中から主体的にカリキュラムを創造するという理念のもとに自由選択の制度が活用されている。
共通科目の履修単位数は、日本文化学科が28から56単位、英米言語文化学科が28から48単位、社会文化学科が32から52単位、人間福祉学科が28から48単位となっている。専門科目は、124単位から共通科目の単位数を引いた差であり、それぞれ、68から96単位、76から96単位、72から92単位、76から96単位となっている。共通科目と専門科目の量的配分は、前述したように学科及び各個人によって異なる。とくに、自由選択というフリーゾーン制度を採用しているために、個人による配分の違いがある。しかし、単位の配分を固定するよりも、学生個人が各自の学習計画、目的を明確にし、主体的に履修計画を立てることができる点で、有効に運用されている。
イ.専門科目
日本文化学科の理念は、国際化の中で、従来の文学、国語方言は、文化の一部であるとの観点から、これらを日本文化及び琉球文化の所産と捉えることであり、目標は、情報化時代に対応可能な人材を育成することである。
1年次では、日本文化論及び琉球文化論に加えて人文情報基礎を必修科目とし、大学生としての必要な学習方法、技術を「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」のクラスで習得させ、自己啓蒙型の人材育成を目指している。2年次では、既習の文化論を更に発展させた専門基礎演習科目を各自で選択学習するカリキュラムとし、自己責任の持てる人材育成を目指している。3年次からは、日本文化コース、琉球文化コース、人文情報コースに分かれ、それぞれの選択必修科目及び選択科目を配している。3・4年次では、2年次で選択した知識を基に「演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」及び「卒業論文」を核として専門知識の構築を具体化していく。これらの演習科目は全て専任教員が担当しており、1年次から4年次までの学生の指導が可能となっている。3年次からの各コースでは、少人数制のクラスを維持すべく数名の担当教員を配置し、学生が体系的に学習できるよう履修指導体制を工夫している。
英米言語文化学科は、2001年4月英文学科から英米言語文化学科へと名称変更を行った。開学(1972年)以来、英文学科は、英米の言語・文化の習得、コミュニケーション能力の養成、中学校・高等学校英語教員の養成、日本語教員の養成などを目標に揚げ、一定の成果を上げてきた。また、英文学科においては、時代の変化や地域社会のニーズに対応するために随時カリキュラムの変更を行ってきた。カリキュラム変更の大きな柱は、実践的なコミュニケーション能力の養成を重視したこと。自国の文化と他国の文化、とりわけ英米の文化を比較対照する視点を培い、それを基に、異文化間コミュニケーションを有効に行うことができる能力の養成を重視したこと。さらに、教員希望者が年々増加し、英語教員養成に関わる科目を増やしたこと等である。その結果、文学研究を中心とする印象が強い「英文学科」という学科名は、カリキュラムの実態とは一致しておらず、「英米言語文化学科」への名称変更を行った。学科名称の変更とともに、英語コミュニケーションコースと英語教育コースの二つのコースを設置した。また、日本語教員養成課程も引き続き設置した。
英米言語文化学科の「教育課程の編成の考え方及び特色」は、以下の通りである。英語コミュニケーションコースにおいては、従来のオーラル・コミュニケーションに加えて、スピーチ、ディベート、インターネット英語など、実践的なコミュニケーション能力を養う科目を大幅に増やしている。英語教員コースにおいては、従来の英語科教育法に加え、英語教育法演習や、言語心理学、社会言語学など、英語教育に関連する科目を大幅に増やしている。従来の必修科目、選択科目の枠組みを大幅に変更し、コース共通必修科目、コース共通選択科目、コース専門科目に分ける。このうちコース共通必修科目については、各年次の演習、情報基礎のみとし、従来の必修科目と較べて科目数を大幅に減らしている。また、コース共通選択科目及びコース専門科目ついては、二つのコースが有効に機能するように、従来の選択科目を再編成すると同時に、新たな科目を増設し、学生の選択幅を広げている。1年次、2年次に基礎演習を置き、グループや個人による発表、日本語・英語によるレポートの作成など、アカデミックなレベルでの学習能力を養成している。3年次の専門演習からは、学生各自の選択したコース及びさらに細分化した専門領域の研究に入り、4年次の卒業論文で、その成果をまとめることができるように、一貫したシステムをとっている。また、日本語教員資格取得を目指す学生の増加に応えるために、関連科目の更なる充実を図っている。
社会文化学科の理念・目標は、自文化としての沖縄及び日本における文化・社会を認識することによって、比較文化的視点を社会学、歴史学、民俗学、文化人類学の学問領域を通して考える能力を養うことである。文化と社会の内容を教育する上で明確化するために、文化コースと社会コースというカリキュラム上のコース制を設けている。社会コースは社会学、平和学、環境学、文化コースは考古学、歴史学、文化人類学、民俗学を学問領域とし、それぞれに関連する専門科目を体系的に配置している。1・2年次の必修科目は、「文化人類学概論」「社会学概論」などの学科教育全体に関わる基礎的科目であり、2年次以上の選択必修科目は、各コース全体に関わるコースの基本的科目と各専攻に関わる専門的科目を配している。1年次から高学年にかけて順に、学科全体の基礎科目、コース基礎科目、専攻専門科目と体系的にカリキュラムが構成されている。但し、学生の履修が一つのコースに偏り過ぎないように、他コース専門科目の履修を推奨している。
また、学科の理念である問題発見、問題解決型の人材育成に関連して、1年次から4年次まで各学年で演習を必修としている。とくに、2年次で専攻の演習を選択し、それ以降4年次まで3年間一貫した演習の指導が、本学科の一つの特色である。演習は、基本的に専任教員が担当し、文化コース4、社会コース3設定している。演習あたりの平均学生数は14名程度で、少人数教育を行っている。
人間福祉学科は、豊かな人間性と21世紀の高度化かつ多様化する国際社会に必要とされる社会福祉や心理学の専門知識を身につけた人材の育成を教育目標としている。人間福祉学科は、社会福祉専攻と心理カウンセリング専攻の二つの専攻から構成され、それぞれ異なるカリキュラムをもつが、社会福祉学、心理学、精神保健学、教育学を関連づけた相互補完的なカリキュラムとなっている。両専攻とも、1年次の必修科目として社会福祉原論、社会学概論、心理学概論を配置して専門基礎的な教育を行なう。2年次以後は、選択必修科目において社会福祉専攻は社会福祉学、心理カウンセリング専攻は心理学の基本的な科目を置いている。さらに選択科目として、それぞれの専攻における専門科目及び精神保健学関連科目を配している。社会福祉専攻は社会福祉士受験資格、心理カウンセリング専攻は認定心理士、そして両専攻共通として保健福祉士受験資格の資格取得に必要な科目を設置し、実践的なカリキュラム内容となっている。
② カリキュラムにおける高・大の接続
本学部では、AO入試及び推薦入試合格者に対して、学科ごとに入学事前オリエンテーションを行なっている。その主な目的は、各学科の教員及び内容の紹介を行ない、入学後何を学ぶべきか考えさせることにある。さらに、課題図書のレポートを提出させ、課題図書に対する解説、討論を行なうことによって、入学後の学習へのモチベーションを形成させることも大きな効果を得ている。
入学後は、学科紹介や履修方法などのオリエンテーションが行なわれるが、4月後半から5月にかけて、各学科で集中的なオリエンテーションが行なわれる。社会文化学科と人間福祉学科は、教員と新入生全員による合宿が行なわれる。講座やレクリエーションなどによって、教員と新入生、そして新入生同士のコミュニケーションを図り、学科のネットワーク作りを通して大学生活に馴染むよう工夫をしている。
1年次では、履修方法、学習方法、文章表現、レポート作成の技法、文献の読み方など大学生活の基本を少人数で指導する基礎的な演習を必修としており、学生が大学生活へ円滑に適応できるよう配慮している。
各学科では、その学科の学習において基本的な科目を数科目1年次の必修として設定しており、専任教員がその科目を担当することによって、学科の学習の導入的な講義を行なうよう努力している。
③ カリキュラムと国家試験
本学部において、国家試験受験資格のカリキュラムを設置しているのは、人間福祉学科のみである。人間福祉学科において取得できる国家試験の受験資格の種類としては、社会福祉専攻に社会福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格などがある。しかし、人間福祉学科は平成13年に開設されており、現在3年次の学生が在学し、国家試験等への受験には至っていない。
人間福祉学科の前身である旧社会学科の4年次学生が社会福祉国家試験受験資格を取得し、毎年受験している。これまでの受験に向けての対策として、後期10月から翌年1月にかけて受験に向けてのオリエンテーションや科目ごとの傾向についての説明会や模擬試験などをおこなっている。
専任教員の担当する科目については、科目の修了試験の中で、過去の国家試験問題からの出題を義務づけることによって、早い時期から学生の国家試験への動機づけと対策をおこなっている。
④ インターンシップ、ボランティア
インターンシップは、インターンシップ運営委員会のもとで全学的に運用されている。
ボランティアの単位化については、人間福祉学科ですでに行われているが、その認定方法などは未定である。今年度中に学則別表の規定改正を行い、各学科にインターンシップの科目を新設して単位化することになっている。ボランティアに関する学内組織として、ボランティアセンターの構想もあるが、まだ検討中である。
英米言語文化学科では、2002年度に本学科の学生が、近隣の小学校からの要請に基づき、総合的な学習の時間(英会話)などにおいて、担任教師及びネイティブスピーカーのアシスタントとしてボランティア活動を行った。小学校英語教育演習を受講中の学生を中心に、約40名ほどの学生が参加した。また、2003年度は那覇市内の中学校から放課後の学習指導のボランティアを要請された。本学科の学生(1年次2人、2年次2人、3年次6人、4年次1人、合計11人)が参加している。
人間福祉学科では、これまで社会福祉援助技術演習(2年次4単位)の中で、夏期休暇中に2週間以上のボランティア活動を行う計画をたて、それぞれの学生は自分の希望する現場(特に福祉施設等)で活動を行っている。また、学科の専門科目の中に、選択科目として「ボランティア演習」を開設している。1年次から履修できる科目であり、本年度20名の学生が受講している。科目の内容としては、オリエンテーション、ボランティアに関するレポート、現場におけるボランティア活動、記録・報告書の提出などを行い、2単位の履修となっている。
⑤ 履修科目の区分
本学部は、必修科目と選択科目のほかに、選択必修科目という区分を設けている。各学科では、履修上のコース制を設定しており(人間福祉学科では制度としての専攻)、そのコース(専攻)の基礎的な科目を選択必修科目として、学生のコース(専攻)あるいは専攻によって学習に必要な科目を選択することになっている。その選択方法については、オリエンテーションや履修モデルによって周知している。
各学科の履修科目区分については、以下の表のとおりである。
|
区 分 |
日 本 文 化 学 科
|
卒業必要単位 |
必修科目単位 |
選択必修科目単位 |
選択科目単位 |
|
共通科目 |
外 国 語 |
8 |
0 |
8 |
0 |
その他の共通科目 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
専 門 科 目 |
68 |
24 |
14 |
30 |
|
自由選択 |
28 |
0 |
0 |
28 |
|
合 計 |
124 |
24 |
42 |
58 |
|
割 合 |
100.0 |
19.3 |
33.9 |
46.8 |
|
区 分 |
英 米 言 語 文 化 学 科
|
卒業必要単位 |
必修科目単位 |
選択必修科目単位 |
選択科目単位 |
|
共通科目 |
外 国 語 |
8 |
0 |
8 |
0 |
その他の共通科目 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
専 門 科 目 |
76 |
20 |
28 |
28 |
|
自由選択 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
合 計 |
124 |
20 |
56 |
48 |
|
割 合 |
100.0 |
16.1 |
45.2 |
38.7 |
|
区 分 |
社 会 文 化 学 科
|
卒業必要単位 |
必修科目単位 |
選択必修科目単位 |
選択科目単位 |
|
共通科目 |
外 国 語 |
12 |
0 |
12 |
0 |
その他の共通科目 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
専 門 科 目 |
72 |
44 |
20 |
8 |
|
自由選択 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
合 計 |
124 |
44 |
52 |
28 |
|
割 合 |
100.0 |
35.5 |
41.9 |
22.6 |
|
区 分 |
人 間 福 祉 学 科(社会福祉専攻)
|
卒業必要単位 |
必修科目単位 |
選択必修科目単位 |
選択科目単位 |
|
共通科目 |
外 国 語 |
8 |
0 |
8 |
0 |
その他の共通科目 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
専 門 科 目 |
76 |
46 |
20 |
10 |
|
自由選択 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
合 計 |
124 |
46 |
48 |
30 |
|
割 合 |
100.0 |
37.1 |
38.7 |
24.2 |
|
区 分 |
人 間 福 祉 学 科(心理カウンセリング専攻)
|
卒業必要単位 |
必修科目単位 |
選択必修科目単位 |
選択科目単位 |
|
共通科目 |
外 国 語 |
8 |
0 |
8 |
0 |
その他の共通科目 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
専 門 科 目 |
76 |
36 |
20 |
20 |
|
自由選択 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
合 計 |
124 |
36 |
48 |
40 |
|
割 合 |
100.0 |
29.0 |
38.7 |
32.3 |
学生個人の学習目標によってカリキュラムの選択の幅を広げるために、必修科目単位数はなるべく低くするように努力している。但し、社会文化学科は社会学、文化人類学、平和学、環境学の基礎を抑えてからコースあるいは専攻を選択するようにしているので、1年次の基礎的科目の必修が多くなっている。また、人間福祉学科社会福祉専攻は、社会福祉士国家試験受験資格のための必修科目が多くなっているので、必修科目の比率が高くなっている。人間福祉学科以外はコース制をとっているので、選択必修科目数の比率が高くなっている。それに選択科目の比率を加えると、日本文化学科と英米言語文化学科は8割以上、人間福祉学科社会福祉専攻でも6割以上の単位数が選択可能となっており、多様で柔軟性に富むカリキュラムを提供するという本学部の教育目標に対して適正な履修科目区分であると考えられる。
⑥ 授業形態と単位の関係
本学部の単位計算は学則に基づき、1授業時間は90分で、それを2時間と計算する。講義及び演習科目は、週2時間の授業を15週行なうことによって2単位を与える。実習及び実技科目は、週2時間の授業を15週行なうことによって1単位を与える。ただし、社会文化学科における「実習」の内容は、夏期合宿による実地調査であり、実質的には60時間以上の時間を調査や資料整理、討論に当てているが、2単位として単位計算されている。また、人間福祉学科の「社会福祉援助技術現場実習」は、厚生労働省規定により半学期の講義と180時間の配属実習と合わせて6単位としている。社会文化学科と人間福祉学科には、それぞれ「社会文化学科海外演習Ⅰ・Ⅱ」と「海外社会福祉演習」が設置され、海外での研修活動をした場合にその科目履修が認められ、2単位が与えられる。外国語科目は、週4時間の授業を15週行なうことによって2単位を与える。
講義科目は、1学期15週の授業を行なうことによって単位を与える、いわゆる学期制を原則としている。演習科目は、通年30週の授業を行なうことによって単位を与える通年制が多い。但し、国外、国内留学を行なう学生が増加し、演習科目についても学期制へ移行する必要が出てきている。英米言語文化学科は、全ての演習科目を学期制にしており、他学科でもこの課題について検討することになっている。
外国語やコミュニケーション科目は、2時間の授業を週2回行なうことになっているが、学習効果等を考慮すると1時間の授業を週4回行なうほうが学習効果が高いともいわれており、この点について今後検討することになっている。
⑦ 単位互換、単位認定等
本学は、県内大学・短大4校と国内5校と単位互換協定、国外5校と学術交流協定を締結している。本学部は、大学基礎データ表4にあるように、2002年度は53名、一人平均13.5単位を認定している。他大学での単位互換については、各学生について事前に学科長もしくはアカデミック・アドバイザーと協定校での科目履修について相談をすることになっている。それに基づいて、学科長が学科会議を経て履修した単位について学科のカリキュラムに基づいて認定をし、最終的には学部教授会において審議、承認される。現在のところ、単位認定について大きな問題はない。
なお、2002年度の基礎データ表4では、日本文化学科における単位互換はないが、同学科において例年国内及び国外への留学希望者がいることを述べておく。
大学以外の学修に対する単位認定は、教職実習、博物館実習、社会福祉援助技術現場実習があり、それぞれ学部の下にそれぞれの実習実施委員会を置き、そこで実施、運営されている。単位認定についても、実習先の評価を尊重し、それに基づいて各実習実施委員会で評価し、最終的には全学部の学生の単位を本学部の教授会で承認している。
また、インターンシップが実施されるようになり、インターンシップ委員会が全学組織として設置されている。インターンシップは、法学部が平成9年度から始めたが、学生が企業や事業所等で研修することによって、職業人としての適性や職業観を養成する貴重な機会であることが全学的に認識されるようになり、本学部でも2003年度から本格的に採用するようになった。インターンシップの単位認定は、現場の評価を基本に、インターンシップ委員会で行なう。それを各教授会で承認することになっている。ただし、インターンシップとしての認定科目が各学科のカリキュラムにまだ設置されていないので、特殊講義などの科目に読み替えている。来年度は、各学科のカリキュラムにインターンシップの科目を設置するよう検討中である。
本学学則第23条によると、他の大学または短大における授業科目の履修は、60単位以内の範囲で認められる。大学以外の教育施設等における学修についても、学則第24条により、その60単位の中に含んで認定することが可能である。また、編入学生の入学前における既修得単位等の認定は、第26条の規定により60単位以内で可能となっている。これらはすべて、大学設置基準の範囲内であり、妥当な扱いだと考えられる。
学術交流協定を締結している国外協定校との間には、1年間の短期派遣留学制度と長期休暇中に行なわれる海外語学・文化セミナーの学生交流制度がある。前者の制度では、派遣留学生は、自分の専門領域と語学レベルに応じて派遣先の授業を履修することができる。その単位認定は、帰国後に各学部・学科において個別に行なわれる。後者については、本学共通科目の国際理解科目群の中に、「海外語学・文化セミナー」という科目が設置されており、参加学生はその単位が認定される。
⑧ 開設授業科目における専・兼比率等
開設科目担当における専任・兼任の比率は、専任教員数や学生数などにより、学科ごとにその状況は異なる。
日本文化学科の専任教員数は12名であるが、専門科目だけでなく、全学科を対象に提供している教職課程科目、図書館司書資格課程科目、留学生関連の日本語科目に加えて大学院の講義も担当している。このような現状では兼任への依存は自ずと高くなり、大学基礎データ表3による2003年度の日本文化学科各コースの専任教員担当科目259に対して兼任教員担当科目129である。しかし、必修科目における専任教員の担当比率は高くなっている。
英米言語文化学科は19人の専任教員を擁している。但し、学科教員は殆どが全学科共通科目の英語を担当しているため、専門科目については兼任教員を依頼せざるを得ない。全開設科目206のうち専任教員の担当比率は約25%となっている。必修科目では92%が専任教員担当である。
社会文化学科はもともと11名(学長を含む)であり、専任教員数が全学科で最も少ない。その上に、学長、学部長、南島文化研究所長、国際交流センター所長の役職を4名も輩出しており、専任教員の担当時間総数に大きな制限がある。さらに、大学院で科目を担当している教員も半数近くいる。このような状況にあるため、どうしても兼任教員の依存率が高くなっている。全開設授業科目で兼任教員担当科目は、全体の約87%にものぼる。必修科目での兼任教員担当比率は19.4%であり、必修科目、特に演習科目については極力専任教員が担当するように努めている。
人間福祉学科の全開設科目のうち専任教員担当比率は約61%あり、比較的その比率は高い。しかし、選択科目については、大部分を兼任で対応しているのが現状である。とくに社会福祉専攻の場合、精神保健福祉士に関する資格科目については専門性の点で外部の専門家に講義を依頼するケースが多く、これらの科目が多く含まれる選択科目に占める兼任の比率が高くなる原因となっている。
各学科に対応する大学院があり、多くの専任教員が大学院科目を担当していることが、学部教育に大きな影響を与えている。大学院専任教員の制度がないため、この状況は致し方ない。専任教員増の見込みがない現在においては、専任教員担当時間に関する現行の専任教員5コマノルマ、最大7コマまで担当可能という規定を検討する必要がある。
⑨ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮
社会人学生及び外国人留学生については、一般学生同様1年次から指導教員としてのアカデミック・アドバイザーがつき、履修や生活上の相談を受けることになっている。とくに、外国人留学生については、日本語教員資格課程担当教員から生活上の相談を受けている。加えて、資格課程履修学生がチューターの役割を担っている。外国人留学生に対しては、学科別のオリエンテーションの他に、全学的なオリエンテーションを行っており、できるだけ早く大学の雰囲気、学科の雰囲気に慣れて、落ち着いて学修に取り組めるように配慮している。また、留学生の学習上の負担に配慮して、日本文化学科管轄の日本語教育課程の科目を履修して修得した単位のうち8単位まで(但し上級科目に限る)を、共通科目の外国語科目、または自由選択科目に振り替えて卒業要件単位に充てている。
人間福祉学科においては、平成9年に設置された旧社会学科の夜間主コースをそのまま継承し、現在でも社会人を対象とした定員15名の社会人夜間主コースが設置されている。同時に、昼夜のクラスに社会人編入学生を受け入れ、社会人に対して大学における勉学の機会を大きく提供してきた。入学試験においては小論文のみで選抜を行うなど、社会人に対する門戸の開放に努め、科目の開講においても、夜間の18:30から6校目以降のクラスだけで卒業が可能となるように、科目開設においても社会人への配慮がなされている。毎年20代から60代までの社会人が入学し、有職者では看護婦や社会福祉の現場に携わる者が多く入学している。これらの学生に対しては、入学時にこれらの社会人だけを対象としたオリエンテーションを開くと共に、アカデミック・アドバイザーを中心に入学後の学生生活全般に関わる相談・指導を行っている。特に夜間主のクラスにおいては、1年次前期のクラスにおいて十分な説明を行い、履修方法から学内設備の利用法、レポートの書き方から図書館での検索の仕方など、懇切丁寧な指導を行っている。図書館の開館時間を夜11時までとするなど、大学としても社会人学生の学習への配慮がなされ、学習条件は向上しているといえる。しかし、社会人学生の中には英語を苦手とする学生やコンピュータ操作に不慣れな者、あるいは若い学生との違和感を持つ者や家庭的問題を抱える者など、社会人特有の問題を抱える学生が目立つのも現状である。このような社会人学生の状況を踏まえ、特に英語やITに関する技術指導、さらに学生生活全般に関わる個別的な相談指導の体制の充実を図る。
⑩ 生涯学習への対応
生涯教育については、大学全体として公開講座委員会及びエクステンションセンターが主体となって運営している。学部としては、学内定例講座を責任担当する。1998年度は、前身の文学部担当で「異文化接触と変容―沖縄・日本・アジア・欧米を巡る比較文化論―」、2002年には「沖縄における教育の課題」というテーマで10回前後の連続講座を行なった。その他、学外講座や夏期集中講座は、学部の教員が個々に対応している。また、公開科目という制度があり、学部科目の大部分を一般に開放し、自由に受講してもらっている。沖縄関係の科目の受講が多くなっている。現行における公開科目の制度は、ほとんどすべての講義科目をリストアップして、社会人がどれでも自由に履修できるようになっている。そういう意味では、自由で公開性があるが、実際に社会人がどの学習目的でどの科目を履修すればよいかということが分からない。そのために、それぞれの科目がどのような内容であるのか、何を学ぶことができるのか、社会人対象のパンフレット等の資料作成やホームページでの内容紹介等を検討する。
⑪ 正課外教育
本学・外国語センターでは英語検定試験、TOEFL、TOEIC、英語基礎講座、英語宿泊合宿など数々の講座を提供している。本学部では多くの学生が、これらの講座を利用して積極的に学んでいる。外国語センターの設立以来、正課外の講座を多数開設してきた。夏期に開講される各種講座は、単位などとは関係ないが受講者は多い。内容がよければ学生は単位と関係なく受講するものだ、ということの証左である。夏期宿泊英語合宿は年々参加者が減少してきている。
本学部には、AO入試や文化活動推薦入試などで、琉球舞踊や琉球音楽に秀でた学生が比較的多く入学している。それらの学生による活動の場として、日本文化学科の琉球芸能専攻の教員が中心となって、2002年度から「琉球芸能文学研究会」が結成された。教員の指導の下に練習を積み、現在は県内をはじめ県外でも公演会開催するまでに成長した。また、近代文学専攻教員の指導による「文芸部」からは、1999年度と2003年度に山之口貘賞受賞者を輩出するなど大きな成果をあげている。本学部の外国語教員が顧問を務めるESSクラブは、毎年学園祭で英語劇を演じている。また、社会文化学科の教員が顧問を務める考古学クラブも、毎年学園祭で研究発表を行なうだけでなく、県内の考古学発掘調査にも参加して成果をあげている。
現在本学部では、基礎学力の不足している学生に対する補習講義等、組織的な正課外教育はおこなわれていない。しかし、近年AO入試、推薦入試等、学力試験を伴わないで入学する学生が増加しており、基礎学力が不足している学生が増加傾向にある。このような学生は、とりわけ文章表現能力に困難を抱えている。基礎学力の充実やIT技術への対応、レポートのまとめ方や発表などの機会を多く持ち、大学生活への適応を円滑に行えるように支援していく課外授業について、各学科で検討し、学部で対応策を考える必要がある。
【点検・評価】
総合文化学部は、2001年度に学部・学科改組を行ない、その際に各学科とも教育課程を新たに改正した。2003年度は、まだその完成年度に至っていない。現行の教育課程を、実施の上でまず完成させることが本学部の現在の課題である。
「学部・学科等の教育課程」、「履修科目の区分」、「授業形態と単位の関係」、「単位互換、単位認定等」について、当面の所大きく改善すべき点は見当たらない。むしろ、自由選択の制度は、学生の自主性を重視する点で、本学の特徴として大いに活用すべき制度だと評価できる。また、1年次の基礎演習を必修に置いている点も、高校卒業後に大学生活に円滑に移行するための有効な科目となっている。さらに、各学科における合宿を伴なう新入生オリエンテーションの成果も大きく評価できる。また、人間福祉学科を除く各学科における履修上のコース制も、2年次或いは3年次に自分の専攻に基づいてコースを選択することになっており、コース別のカリキュラムによって学習の目標が立てやすくなっているなど教育効果が高まっていると評価できる。
他方、カリキュラムの運営は、専任教員に余裕がないことと、大学院教育と兼務することが多く、兼任教員の担当比率が高くなっていることが懸念される。特殊な内容の講義を学外の兼任講師に依頼することは教育の内容に幅をもたせることになって教育効果をあげることになるが、演習や基礎的な科目は専任教員が担当して、密な教育をすべきであり、この点は改善すべきであると認識している。
また、インターンシップを昨年度から新たに導入したが、それを単位として認定する科目がないことは、それに参加した学生に不利益になっている。
【改善・改革方策】
専任教員の担当時間数の改善については、2002年度に大学執行部案が出され、本学部はそれに賛成したが、他学部の理解を得ることができず、不成立に終わった。この課題について、再度本学部内でも議論をして、大学全体に理解を求める。
また、インターンシップについては、早急にその科目を各学科カリキュラムに新設することになっている。
(2) 教育方法とその改善
【現 状】
① 教育効果の測定
全学共通の「学部履修規程」によると、単位を修得するためには、その授業を履修し、試験に合格することと定められている。授業への出席は、3分の2以上を要求されており、それ以下の場合は試験を受けることができない。試験は、原則として学期末に定期試験が行なわれる。成績評価は、80点以上が優、70点以上80点未満が良、60点以上70点未満が可、60点未満が不可となっている。演習や実習の科目については、平常の成績や実技によって評価することができる。
規定上は、上記のように学生の成績が決定されるが、実際は教員によってさまざまな教育効果の測定が行なわれている。学期中の小テストや課題、学期末のレポート、出席状況、授業中の発表など、さまざまな方法によって成績評価が行なわれており、それは科目ごとに『講義概要』に明記されている。したがって、教育効果の測定方法については、学生のみならず全ての教員にも公開されていることになる。ただし、教育効果の測定方法について教員が検討する場はなく、その方法の適切性を判断するのは各教員に任されている状況である。
卒業生の進路については、大学基礎データ表8によると、卒業時における就職率が3割程度と決して高いとは言えない。それは、沖縄県における就職環境が全国に比べて著しく低いことと大きく関係する。卒業後に就職試験準備やアルバイトなどの経験を経て、就職にいたるケースが多い。沖縄県教員採用試験に関しては、平成15年度採用試験合格者は本学全体で42名となっており、中学・高校教員合格者については県全体の約3割を本学卒業生が占めている。
② 厳格な成績評価の仕組み
本学部では、成績評価は各教員個人に任されており、各授業における成績評価の方法は『講義概要』に明記することになっている。成績評価の基準として、出席、中間・期末試験の結果、授業への参加度、レポート等などがあり、それらを総合的に評価する方法がとられているのが一般的である。また、実習等の科目においてはその成果、施設等における実習においては現場の担当者の評価表、卒業論文等においては成果物の内容と発表の内容を参考に評価する方法もとられている。
履修科目登録の上限は、「学部履修規程」によって1学年40単位と定められている。ただし、卒業年度は52単位までの履修が可能となっている。1年間に多くの科目を履修して消化不良にならないように学生の学習に対する配慮ではあるが、近年カリキュラム改革の中で資格科目の多くが専門科目の中に組み込まれ、資格科目を多く取ると、年間40単位取得という制限があるため、本来の専門科目を履修できないという状況が生じている。これは本来あるべき学科教育が薄められ、資格優先を強いる結果になっている。年間履修単位数の上限を52単位程度に引き上げることを全学の教務委員会で検討中である。
成績評価を厳格にするために、評価基準を明確にするとか「優」評価の比率を定めるなどの議論は、学部・学科ではまだ行われていない。ただ、成績評価を客観化するために、「成績確認」制度が全学的に設定されており、学生は、学期始めのオリエンテーションにおいて成績の結果を受け取り、その評価を不服とする場合は、教務課窓口に願いを提出して担当教員の評価についての再確認をとることができる。
本学は、年次制度をとっていないので、自動的に次の年次に進級することになっている。ただし、毎学期ごとに学年ごとのオリエンテーションが行なわれ、カリキュラムにそった履修方法についての指導が行なわれる。また、演習の教員がアカデミック・アドバイザーとなっており、演習の時間を利用して各自の成績チェックと履修指導を行なっている。さらに、1年間の履修単位数が16単位未満の場合は、除籍等の強い指導が入る。この点については、次項で述べる。
また、GPAを利用して、指定校推薦入学者の追跡調査をしたことがある。これをさらに拡大して、入学種別ごとの成績分析や出身校ごとの成績分析など、学生の質や学習の成果を検証するシステムの検討を計画している。今までのGPAの利用状況は、各学科の学年ごとに最優秀成績の学生を選別し、その学生に対して特別奨学金を支給している。今の段階では、GPAを利用した教育効果の測定法は、本学においてまだ確立されていないといえる。さらにこの制度を拡大して、GPA上位5%程度の学生に対して奨学金を支給する制度の新設など、学生の学習意欲を刺激する方法を検討する。
③ 履修指導
本学部の履修指導は、学期始めの学年全体オリエンテーションのほかに、個別的に演習ごとに決められているアカデミック・アドバイザーが担当している。1年次の履修指導は、4月の学年始めに2回の全体オリエンテーションを行なう。それぞれ2時間程度のオリエンテーションであり、細かい点や個人的な履修までは指導が行きとどかない。そこで、1年次の必修である基礎演習などの時間に、担当教員がアカデミック・アドバイザーとして履修指導に当たる。2年次は、学期始めの学年全体オリエンテーションがあり、そのあとは演習のなかで履修指導が行なわれる。2年次以降は、専門演習の担当教員がアカデミック・アドバイザーとなる。アカデミック・アドバイザーによる指導は、学期始めの演習の時間に行なわれる。その他個人的な相談は、教員ごとに定められたオフィスアワーの時間を利用することも可能である。また、学年毎に学年指導委員が置かれ、学期始めのオリエンテーションを担当している。登録カード提出後、コンピュータ処理をして登録確認を行なう制度になっている。その際に登録上問題がある学生に対して、教務課職員が個別に対応、指導している。その際に、必要に応じて学科長やアカデミック・アドバイザーの指導を受けることもある。科目履修は、学生の目的的学習の実現にとって基本となる事項であり、学部・学科として履修指導を重視している。しかし、まだ学生の勘違い等があるので、それを未然に防ぐために、各学生の履修カードをアカデミック・アドバイザーが確認するシステムを新たに設定する予定である。
本学では、1996年度から全教員がオフィスアワーを設定している。1週間に1コマ分の時間帯をオフィスアワーとして公開するとともに、その時間には研究室に待機して学生の質問などを受けることになっている。各教員のオフィスアワーは、毎年発行する『講義概要』に明記されるとともに、各研究室にも掲示されているので、多くの学生に周知徹底されている。ただし、オフィスアワーが確実に実行されているか否かについての実態調査がなされていないので、その実施状況について調査を行う必要がある。
本学には、留年の制度はない。しかし、年間取得単位数16単位未満の学生に対しては、除籍処分の規定がある。実際には、1年間は指導期間に充てており、単位不足学生に対しては、学科長とアカデミック・アドバイザーが指導することになっている。
すでに述べているが、本学には学生の学習支援として、アカデミック・アドバイザーの制度が確立している。本学部では、1年次から4年次まで全ての学生に対して演習が用意されているので、その演習の担当教員がアカデミック・アドバイザーとなる。履修指導や、留学、休学などの相談、その他生活上の相談もアカデミック・アドバイザーが担当する。本学部においては、この制度は有効に活用されている。
科目等履修生は、教職などの資格科目を履修する課程等履修生と一般科目を履修する一般科目等履修生に区分される。前者は、教職や博物館学芸員、図書館司書などの資格課程ごとにオリエンテーションを開催しているので、課程等履修生もそれに出席して履修指導を受けることになっている。一般科目等履修生は、それぞれの学科長が履修指導を行なうことになっている。
国外協定校から留学に来る外国人の特別聴講学生及び正規入学前の外国人科目等履修生は、主に日本語を学習することになるが、これらの学生に対しては、日本語教育担当教員を中心として特別にオリエンテーションが行なわれる。
④ 教育改善への組織的な取組み
本学部における教育目標の一つは、学生の問題解決能力の育成であり、そのために演習を重視した教育指導体制を意識的に構築している。少人数による演習を中心とした教育は、履修指導から始まり、日常の学生の学修状況にも目配りがきき、学生の学修の活性化につながっている。演習の活動を補助するために、本学はさまざまな補助を行なっている。演習で学外合宿をする際には、ゼミ補助費がある。また、東村のセミナーハウスを演習で利用するときには、さらにその宿泊費に対する補助が用意されている。さらに、演習での学習成果を公表する際には、その印刷・出版に対して1ゼミあたり5万円の補助費がある。これらの補助を活用し、本学部では演習単位の活動報告書やレポート集などの出版がたいへん盛んになっている。
『講義概要』は、教務部が編集主体となって、毎年学部ごとに編集、発行されている。それは、大学のホームページにも掲載され、学内外から見ることができるようになっている。その内容は、授業ごとに、『講義概要』、講義計画、テキスト・参考文献、成績評価の方法、講義計画が示されている。内容としては十分だと思われるが、学生が履修の際に参考とするのは、『講義概要』のほんの一部の情報に過ぎない。そういう意味では、無駄が多いことになるので、ホームページを利用したシラバスの活用方法を開発して、印刷資料を省略するなどの検討を行なっている。
大学において、ここ数年の学生の変化は著しい。「大学の高校化」ということも言われるようになった。そのような中にあって旧態依然とした講義の方法で上手く行くはずはない。指導方法についても、お互いに情報を交換しあい、研究していく必要がある。2002年度に、本学全体のファカルティ・ディベロップメント委員会規程が成立した。それを受け、総合文化学部では、学部FD推進委員会を組織して、3度のFD講座を開催した。第1回目は、広島大学高等教育研究開発センター教授の大膳司氏をお招きして、「FDの現状と可能性」という題での講演会。第2回は、パワーポイントの操作方法の指導。第3回は、「基礎演習の実践と課題」というテーマで、各学科における実践とその課題発表、及び参加者による討論会であった。本学部のFD活動は、大学全体の活動に先駆けて昨年度から始まったが、学部教員からは一定の評価を得た。専門家からの講演を通してFDの必要性を確認した後に、具体的な教育方法としてのコンピュータソフト使用方法の講習会、そして各学部に共通する1年次の基礎演習のあり方について、その理念と実践の討議を行い、教育に関わる各方面の問題を取り上げたことが評価された。特に、基礎演習の討議では、他学科での工夫や問題点が積極的に討議され、教員相互の学習の場となった。FDの継続的実施を行なうには、その基礎となる予算の設置が必要であり、この点は2003年度から実現した。もう一つは、その計画、実施体制であり、本学部は、学部長、学務主任、各学科長(4名)、教職課程主任の7名でFD委員会が組織されているが、この方面の専門家がいないために、積極的な企画を立てにくい面がある。
学生による授業評価も、教育効果の測定には有効である。本学では、教務部が中心となって過去2回大学全体の授業評価を実施したことがある。その結果は、各教員に還元した。しかし、その後授業評価については、大学においても、学部においてもシステムとして確立されていない。しかし、教員によっては個人的に学期末のアンケートや各授業の出席表に疑問や質問、感想を書いてもらうという形式の授業評価を行なって、各自授業の改善に努めている。
⑤ 授業形態と授業方法の関係
授業形態は、講義と演習そして実習に区分できる。講義は、どうしても教員から学生に教授するという伝統的な授業形態をとることが多い。その場合、板書と資料配布のほかに、学生の理解を助けるためにAV機器を利用した視聴覚資料を利用するよう努力している。それは、組織的に行っているのではなく、各教員が学生気質の変化やAVソフトの発達を考慮して、各自で工夫しているという状況である。ただし、語学の講義に関しては、2003年10月から従来あるLL教室の機器を全面入れ替えし、CALLシステムを配備することになっており、機器を利用した教員と学生の交流が密になると同時に、学生の進度に合わせた効率的な授業が可能になると予想される。
演習の授業は、10名から20名以下の少人数クラスであり、講読や討論を中心にしている。演習では、学生個人による学習、研究の発表を重視しており、多くの演習ではその成果を学年末に印刷している。その作成過程において、演習参加学生の間に協力や連帯の意識が養われ、良い効果をあげている。大学の教室設備が視聴覚教材を使用する授業形態に対応しているので、パソコンやビデオ教材を使用する教員が増えている。市販されているビデオ教材だけでなく、テレビを使ってラジオ番組を利用した授業もある。また、地元在住の専門家を講義時に招いての実演、講演や討論会形式の授業形態も増えている。
人間福祉学科における授業形態は、それぞれの担当教員の判断により効果的な方法がとられている。基本的には講義形式や演習形式のほか、障害体験やモデルを使用した体験学習やシュミレーション学習、社会実習や施設などの現場訪問や活動への参加による学習、あるいは福祉施設や病院等における現場実習など多様な形態がある。また、1年次学生全員を対象とした合同合宿や社会福祉専攻2年次学生が行う学会形式で学外からの参加者を募って開催する「社会福祉セミナー」や「国際社会福祉セミナー」の形式、外国の施設やスラムなどでボランティアを通して実際に体験する「海外社会福祉演習」などの形式、あるいは学生自ら参加する「ボランティア演習」の形式などもある。上記のように、人間福祉学科においては学習の目的や効果、精度を高めるなどの観点から種々の授業形態がとられ、一定の成果を上げている。
【点検・評価】
教育効果の測定、成績評価の基準作り、履修指導の方法、教育改善への組織的取り組みのいずれの項目においても、教育方法の検討と改善については本学及び本学部の取り組みは本格的に行なわれていない状況である。FD委員会も、2002年度に大学全体として組織化されたが、本格的な活動は行なわれていない。本学部では、学部独自でFD推進委員会を組織して講演会やディスカッションなどを開催したが、この活動によって大きく効果が現われたとは言いがたい。
【改善・改革方策】
学部FD推進委員会を、定期的に開催するなどより活性化する。その成果は、文字化して学部全教員に配布し、周知徹底する。また、これまでに行った授業評価の方法について再検討し、より効果的な方法を確立し実施していく。授業評価だけでなく、学内の設備、機能、運用のあり方等に至る詳細な部分に至るまで、ユーザーである学生がどのように考え、改善の意見を持っているかを聴取する手だてについて、全学FD委員会に検討するよう学部から要望する。
(3) 国内外における教育研究交流
本学の国内外における協定校は、海外5校と国内5校となっている。単位互換による交換学生制度、短期の研修による学生交流、教職員の交流など積極的に行なっている。これら協定校との教育研究交流については、全学で取り組んでいる。
本学部独自の交流については、人間福祉学科において、毎年夏期休暇中にデンマークやスウェーデン、ノルウェーを中心とする北欧コースとタイを中心とするアジアコースの二つのコースを基本として「海外社会福祉演習」を実施している。同時に、研修先の施設などの交流を行い、学生が自主的にボランティア活動に参加したり、卒業生が長期にわたり職員として滞在するなど、交流が盛んに行われている。人間福祉学科の専門選択科目とし「海外社会福祉演習」が開設されたこともあって、毎年希望する学生が増加しているのが現状である。
グローバル化が進む中、海外特にアジアの児童や貧困問題に関心を持つ学生が増加し、実際にボランティア活動や自主的な研修、あるいは海外の施設へ就職する卒業生がでるなど、海外の課題に関心が向き、国際貢献に関心を持つ卒業生が増加することは好ましいことである。
外国人教員の受入れは、「研究員の受入れに関する規程」に基づいて受入れている。本学部では、過去に3回フルブライト教員を受入れた実績があり、その他2002年度に韓国の韓南大学校から半年受入れている。2003年9月から1年間、国際交流基金の研究フェローとして、福建師範大学歴史系教授を受入れることになっている。
第4節 教職課程
【現 状】
① 教職課程の理念・目的及びその成果・実績
本学の教職課程(教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程)は1972(昭和47)年、本学創立と同時に設置された。現在、各学部・学科・専攻で認定されている免許教科と免許状の種類は下表の通りである。
学 部 |
学 科・専 攻 |
免許教科 |
免 許 状 の 種 類 |
|
法 学 部 |
法律学科 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
地理歴史 |
高等学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
|
地域行政学科 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
地理歴史 |
高等学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
商経学部 |
経済学科 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
地理歴史 |
高等学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
商 学 科 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
商 業 |
高等学校教諭一種免許状 |
|
総合文化学部 |
日本文化学科 |
国 語 |
中・高等学校教諭一種免許状 |
英米言語文化学科 |
英 語 |
中・高等学校教諭一種免許状 |
|
社会文化学科 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
地理歴史 |
高等学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
人間福祉学科
社会福祉専攻 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
福 祉 |
高等学校教諭一種免許状 |
人間福祉学科
心理カウンセリング専攻 |
社 会 |
中学校教諭一種免許状 |
公 民 |
高等学校教諭一種免許状 |
[備考]福祉科免許課程の完成年度は2004(平成16)年度である。 |
本課程の理念・目的は開放制教員養成制度の理念の下、教員になろうとする意欲のある者でしかも教員に必要な資質と能力を高水準に有する者に限定して、免許資格を付与するところにある。
1998(平成10)年度以降の本学の教員免許状取得件数を免許教科ごとに示すと下表のようになる。なお、創立以来の免許状取得者数は約3,300名に及んでいる。
年 度 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
社 会 |
63 |
60 |
55 |
45 |
33 |
地理歴史 |
18 |
27 |
24 |
17 |
16 |
公 民 |
47 |
60 |
66 |
60 |
44 |
国 語 |
14 |
29 |
33 |
40 |
42 |
英 語 |
22 |
28 |
28 |
32 |
36 |
商 業 |
19 |
12 |
34 |
18 |
18 |
合 計 |
183 |
216 |
240 |
212 |
189 |
また、1999(平成11)年度以降の本学出身者の教員候補者選考試験合格者数を沖縄県全体の合格者数との関係で示すと下表のようになる。本学教職課程学生は殆どが県内出身者で教員採用も県内学校を希望している。本学出身者は取得可能な免許教科のすべてで合格者の3~4割を恒常的に占めており、県内の中学校・高校教員の一大供給大学となっている。創立以来の教員候補者選考試験合格者数は約830名にのぼっている。
採用予定年度 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
社 会 |
9( 20) |
4( 7) |
4( 17) |
4( 14) |
9( 16) |
地理歴史 |
2( 8) |
2( 13) |
2( 8) |
1( 8) |
2( 8) |
公 民 |
2( 5) |
3( 8) |
1( 3) |
2( 6) |
1( 7) |
中 学 国 語 |
10( 24) |
8( 14) |
11( 20) |
7( 11) |
5( 10) |
高 校 国 語 |
6( 23) |
5( 16) |
3( 16) |
8( 19) |
3( 19) |
中 学 英 語 |
3( 14) |
3( 13) |
3( 14) |
4( 14) |
10( 28) |
高 校 英 語 |
7( 33) |
5( 16) |
7( 24) |
9( 23) |
4( 25) |
商 業 |
3( 5) |
4( 13) |
4( 11) |
2( 11) |
2( 10) |
合 計 |
42(132) |
34(100) |
35(113) |
37(106) |
36(123) |
占有率 (%) |
31.8 |
34.0 |
30.9 |
34.9 |
29.2 |
[備考]括弧数字は沖縄県全体の合格者数。占有率は本学出身者の県全体に占める割合。 |
② 教育課程
本教職課程の教育課程は教育職員免許法施行規則に則って編成され、文部科学省の審査を経て認定されたものである。
教育課程の大きな特徴は、前項で述べた理念・目的を実現するために、教職に関する科目について、基礎的科目から応用的科目に配列し、受講のための前提科目を設けた本学独自の履修体系を設けていることである。それは下図の通りである。
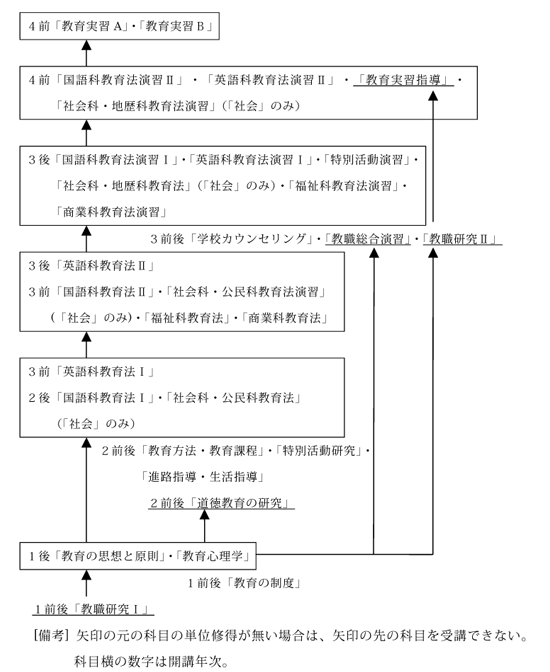
この仕組みにより、学生を育てながら絞り込むことが可能になっている。実際、入学時に教職科目を受講した者の内、教育実習まで行き、免許状を取得できる者は、例年その約3割に留まっている。
免許法の基準を超えて、教職に関する科目のうち「教科教育法Ⅱ」(2単位、高校国語・英語)「教科教育法演習Ⅱ」(2単位、中学国語・英語・社会と高校国語・英語)と「特別活動演習」(1単位、中学・高校)「道徳教育の研究」(2単位、高校)が必修となっている。
教科に関する科目は、学科固有の専門科目と全学共通科目に分けられるが、後者も教職課程学生のために設けられている科目であり、その専門性が担保されている。
共通科目に関して、教育職員免許法施行規則第22条第4項「教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い豊かな人間性を涵養する」に則り、各学科の規定する共通科目の最低履修単位数をこえて30単位程度履修することを勧めている。また、英語以外の外国語と健康・スポ-ツ科目群から実技科目1科目を、奨励科目として指定している。
その他、今日の学生は人間形成の基盤である自然体験、社会体験や生活体験が乏しくなっていることから、『履修ガイド』の中でこれら体験活動の奨励を行っている。
③ 教育方法及び履修指導
本課程の教育方法及び履修指導上の大きな特徴は、教科教育学を教育学と学科の専門科学との結節点、ならびに教育諸科学の理論と教育現場での授業実践との結節点として位置づけていることである。そこで、教科教育法と教科教育法演習は少人数クラスで同一の専任教員が通年で一貫指導できるように編成している。これにより教職課程と学科の課程の有機的関連が作り出されている。また、教科教育法演習担当者が教育実習の送り出しの実質的責任者となることが可能で、教職課程全般の履修指導を行き届かせる結果に結びついている。
このような指導体制の下で、教科教育法演習においては各学生が1時間の模擬授業を行うことが可能になっている。模擬授業は一人の学生が授業者となり生徒役となった他の学生を相手に授業を行うものである。この取り組みは本学では早くから行われており、全国的に注目を集め、2001(平成13)年に本学を会場に開催された全国私立大学教職課程研究連絡協議会(全私教協)の研究集会で公開実演も行われた。
さらに少人数・通年・一貫指導の副産物として、ゼミ合宿、ゼミ学習会、ゼミ対抗スポーツ大会など、教科外教育の指導も視野に入れた正課外教育が盛んに行われている。
2003(平成15)年4月の教職研究Ⅰの履修登録者数は全入学者(1,394人)の約40%(562人)にのぼった。このことに示されているように、例年本課程履修者は多数にのぼっている。しかし、先述したような「履修体系」を設けているため、教育実習まで行く者は、その内の約3割(200人前後)である。
本課程履修者に対する全学的な履修指導は、教職課程運営委員会が決定した年間の指導計画に基づいて行われるが、その主なものは次表のようにまとめられる。
| |
履 修 指 導 の 内 容 |
| 4月 |
『履修ガイド』配付、在学生教職課程オリエンテーション、新入生教職課程オリエンテーション、編転入生教職課程オリエンテーション、教育実習本登録受付、第1回介護等の体験オリエンテーション
|
| 5月 |
第1回・第2回教育実習オリエンテーション(6月実習、9月実習)、沖縄県教員候補者選考試験説明会 |
| 6月 |
教育実習訪問指導、教育実習生中間懇談会(6月実習)、教育実習教科別反省会(6月実習)、教育実習校との懇談会(6月実習)、第2回介護等の体験オリエンテーション
|
| 7月 |
第3回教育実習オリエンテーション(9月実習)、
第3回介護等の体験オリエンテーション、介護等の体験施設表敬訪問(7月~) |
| 9月 |
教育実習訪問指導、教育実習生中間懇談会(9月実習) |
| 10月 |
教育実習教科別反省会(9月実習)、教育実習校との懇談会(9月実習)、教育実習校選定方法説明会、介護等の体験学校表敬訪問(10月~)
|
| 12月 |
教育実習録返却、教員免許状一括申請説明会 |
| 2月 |
介護等の体験日誌返却 |
| 3月 |
教員免許状授与 |
このほか、教職課程専任教員、教務課担当職員及び上述したように教科教育法担当者によって、個別指導・相談が随時実施されている。
国内の単位互換協定を結んでいる総ての大学について「教職科目読み替え・取り扱い方法一覧表」が整備されており、協定校留学に際しての履修指導もきめ細かに行われている。
④ 人的体制及び管理運営
以上の教育課程と教育方法及び履修指導を実施するための人的体制としては、まず、文部科学省の課程認定審査基準に則り教職課程専任教員が3名配置されている。
本課程の人的体制の特徴は常勤の教科教育法担当者11名が配置され、既述したように少人数・通年の一貫したきめ細かい指導を可能にしていることである。これらの担当者の殆どが現場経験が豊かで、教科教育学の優れた実践家的研究者でもあり、教育現場に密着した指導を実現している。
教職課程の管理運営のための組織として教職課程運営委員会が設けられている。委員会は、総合文化学部長、教務部長、教務部次長、教務課長、教職課程主任、教職に関する科目担当者、各学科選出委員で構成されている。委員会の中に議題調整機関として、委員長、教務部長、教務部次長、教務課長、教職課程主任、教職課程専任教員により構成された調整委員会が設けられている。教職課程主任は、任期は1年で総合文化学部で選出される。職務の性格上これまで教職課程専任教員が担当している。
教職課程運営委員会は教育実習に関する事項の他、教職課程の教育課程や教員人事も議題とする。ただし、教員人事についてはその決定権は総合文化学部教授会にある。
その他、学外の組織・団体として全国私立大学教職課程研究連絡協議会(全私教協)と九州地区大学教職課程研究連絡協議会(九教協)に加盟している。全私教協では2000(平成12)年から2年間副会長校を務めた。また、沖縄県教育委員会管轄の沖縄県教員の資質向上連絡協議会と沖縄県介護等の体験連絡協議会に積極的に参加している。
【点検・評価】
教職課程の理念・目的については適切であり、順調に実現され、本課程の成果・実績も非常に良好である。
教育課程については、教職に関する科目に選択科目がない点を除いて、概ね適切である。教職に関する科目の「履修体系」は目的・理念を実現する上で、今後も堅持されるべきものである。
教育方法については、教科教育法の指導体制と模擬授業は良好な成果を上げており、今後も継続されるべきである。
履修指導も極めて適切に行われており、履修上のトラブルは殆どない。
国内協定校との教職科目の単位互換については、本学教職課程の水準を維持するため教科教育法と同演習の読み替えを行っていない。そのため、「履修体系」の関係もあり、3年次に協定校に留学した学生は卒業時の免許取得が不可能になり、留学の阻害要因となっている。
教科教育法と同演習の正課外で行われている合宿研修はそれらの科目や教育実習の事前指導等を補完する上で重要な役割を果たしている。しかし、学生と教員の加重負担につながり、また、事故等発生の場合、責任問題や補償問題を生じさせる危険性をかかえている。
人的体制については、本学では教職課程受講者数が多数にのぼることもあって、問題を抱えている。教職課程専任教員については3名では十分な体制とはいえない。本学の学則入学定員合計は1,195人であるが、文部科学省の課程認定審査基準では入学定員が1,201人以上からは教職課程専任教員は4名以上必要となっているからである。加えて教職課程受講者が入学者の4割以上にのぼるという本学の特殊事情が存在するからである。
教職に関する科目のうち、基礎的科目である教育心理学を兼任教員が担当していることと、教職総合演習の兼任講師依存率が高いことは、本課程の理念・目的の達成の上で懸念材料である。
教科教育法でも次の問題がある。①地理歴史科の教科教育法と同演習各1クラスと商業科教育法を兼任教員が担当している。②公民科の教科教育法と同演習を教育の基礎理論に関する科目担当の教職課程専任教員が担当している。③国語と英語と社会において、少人数教育が困難になったり、兼任教員担当クラスが発生したりしている。④中学社会科担当教員は2名とも歴史学専門で、高校地理歴史科担当教員は2名とも地理学専門という、専門分野のアンバランスが存在している。⑤高齢の教員の担当する教科教育法科目がある。
教科に関する科目では、地理分野での兼任講師への依存度が高い。高齢の教員が担当している科目がある。
管理運営については概ね良好である。しかし、兼任教員任用の際、教職課程運営委員会で決定したものであっても、教職課程専任教員の所属する学科会を経てしか総合文化学部の教授会に上程することができないため、機敏な対応ができない。同じく教職課程専任教員の所属する学科との関係で、学科の一員としての業務を担うため、全学に責任を負うべき教職課程教員の本分が妨げられているという問題がある。
日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション及び情報機器の操作に関する科目の科目が教職課程の必修科目となっているため共通科目と教職課程は密接に関係するが、教職課程主任が共通科目運営委員会委員でないため、一部の科目がマスプロ講義のまま放置されているなどの問題が生じている。
【改善・改革方策】
教職課程の理念・目的及びその成果・実績については、現状を維持しつつなお次の点に取り組む。すなわち、①21世紀の教育の趨勢である国際化・情報化や地球規模での環境問題・平和問題に教員として取り組むことのできる資質や能力の形成。②不登校やいじめなどが問題提起的に要請しているカウンセリングマインドや生活指導の実践的能力、福祉分野との連携能力の形成。③すべての免許取得者が教師になるわけではないので、他の職種に就く者や親となる者にとって教職課程が有する意義を明確にすること。
教育課程については、「青年心理学」と「教職課程特殊講義」を選択科目としての開設を今後、検討する。
教育方法及び履修指導については、国内協定校との単位互換に関して、協定校の中には教科教育法と同演習を本学と同じ内容で課している大学も出てきているので、実態を調査し、読み替えができるよう改善する。
正課外で行われている合宿研修は、「教科教育法特別演習」等の科目にしていくことを検討する。
学級経営の改善研究、マルチメディアによる教育体験の推進及び授業研究の促進のため、マルチメディア機器を備え、授業観察スペースを有した、中学校・高校と同タイプの教室を模擬授業教室として整備するよう検討する。
人的体制については、教職課程専任教員を1名増やし4名にすることが必要である。また、教育心理学と教職総合演習の兼任教員による担当の問題の解決に取り組む。
地理歴史科の教科教育法と同演習ならびに商業科教育法担当の兼任教員を解消するかまたは適切なフォローを行う。公民科の教科教育法と同演習について専門の教員の配置を検討する。国語と英語と社会の教科教育法についても、兼任教員の解消や少人数クラス確保のための対策を講じる。教科教育法の社会科担当者と地理歴史科担当者の専門分野のアンバランスの問題も検討が必要である。
教科に関する科目の地理科目については兼任教員問題を解消する。国語科教育法、商業科教育法及び職業指導では担当者の若返りが必要である。
管理運営については、教職課程主任が共通科目運営委員会の委員になることを検討する。
教職課程運営委員会における審議や報告の重要事項が各学科に遺漏なく伝わるようにするため、学科長が職責として委員になるようにするか、または、教職課程主任が教務委員会の委員になることを検討する。
教職課程の兼任教員の任用については学科会での審議を省略する方向で学内合意を得る。また、教職課程専任教員が所属する学科の業務分担は極力軽減する。
なお、次の点に新規に取り組む必要がある。既述のように現在約830名の卒業生が主として中・高校の正教員として学校現場で活躍しているが、これら教員を対象にした同窓会組織はまだ全学的には創設されていない。教員養成における大学と学校現場との連携がますます求められている今日、同窓会組織の結成をはじめとした本学出身教員との交流・提携事業は有益かつ急務な課題となっている。
第5節 博物館学芸員課程
【現 状】
沖縄国際大学の博物館学芸員課程は、地域社会の要請に基づき、平成4年に県内最初の大学における博物館学芸員課程として文部省から認可を受けた。平成15年度現在、304名の博物館学芸員資格者を送り出し、県内市町村の教育委員会や郷土博物館にもこの資格を生かして就職する者も徐々に増えてきている。
沖縄国際大学における博物館学芸員課程は、博物館法の精神に基づき、次のようなカリキュラムにより構成されている。
① 必修科目
| (a) |
1年次から受講の科目としては、「教育学概論」4単位(「教育の思想と原則」あるいは「教育の制度」で読み替えることができる)、「芸術学Ⅰ・Ⅱ」2科目4単位、「自然科学概論Ⅰ・Ⅱ」2科目4単位(共通科目の自然・環境科目群のうち化学Ⅰ・Ⅱを除いた各科目及び沖縄の自然Ⅰ・Ⅱに読み替えることができる)となっている。 |
| (b) |
2年次からからの受講科目として、「博物館概論」2単位、「博物館経営論」1単位、「博物館資料論」2単位、「博物館情報論」2単位、「視聴覚メディア論」2単位、「生涯学習概論」2単位、「考古学概論Ⅰ・Ⅱ」2科目4単位、「文化史Ⅰ・Ⅱ」4単位が開講されている。 |
② 選択必修科目
2年次からの受講で、「民俗学Ⅰ・Ⅱ」2科目4単位、「南島民俗学Ⅰ・Ⅱ」2科目4単位となっており、Ⅰ・Ⅱをセットにして2科目4単位以上が義務づけられている。
③ 博物館実習
①、②において所定の科目を履修した受講生には、「博物館実習Ⅰ・Ⅱ」が許可される。例年、12月に第一回の博物館学芸員課程オリエンテーションを開催し、所定の科目を履修した学生を対象として、博物館実習に対する心構え等の指導、課題レポートの提出、実習館の希望調査などを出してもらう。2月に第二回のオリエンテーションを行い、実際の実習生を受け入れる博物館の割り振りを行なうのである。実習生は、3月の博物館見学実習を皮切りに、4月~7月までが、主に夏休みに実施される「博物館実習Ⅱ」の基礎トレーニングとなる「博物館実習Ⅰ」1単位を受講する。この科目は、考古学、歴史学、地理学、民俗学、自然科学などの各分野で一回の講義(90分)とフィールドワークが義務づけられており、受講生はすべて履修することになっている。そして、夏休みを中心に約10日間の博物館での実習である「博物館実習Ⅱ」2単位が実施される。現在の博物館実習生を受け入れてくれる博物館は、沖縄県内を中心に県立博物館をはじめ市町村博物館等を中心に12~13館となっており、毎年30名近くの実習生を受け入れている。
④ 単位認定
博物館実習Ⅰ・Ⅱを修了し、所定の単位を履修した受講生については、現在、総合文化学部教授会が単位認定を行ない、卒業式の日に大学として、博物館学芸員単位認定書を発行する。
⑤ 実習の組織運営
総合文化学部長を委員長とし、実際に博物館学関係の教科を持つ教員で組織する博物館実習実施委員会が設けられ、博物館実習を中心とする博物館学芸員養成の教育を支えている。
【点検・評価】
今年で12年を迎えた博物館学芸員課程も十分定着した感があるが、博物館学芸員の課題についてみてみると、第一に受講生側の問題点として、単に資格の一つとして、確固たる目的意識もないまま、資格取得に走る学生が散見されることである。第二に、文系の大学の宿命ともいえるが、自然関係の分野を中心とするフィールドワークの弱さが指摘されよう。
【改善・改革方策】
目的意識の欠如した受講生がわずかながら見受けられる現状を是正するため、入学時から博物館学芸員というコースの内容について、関心を持つ学生を対象にオリエンテーションを実施し、その上で明確に博物館学芸員になるという意識を持つ学生だけに、受講を許可するように、指導の徹底を図る。第二の自然科学系におけるフィールドワークの弱さについては、博物館学芸員資格では指定されていない自然科学的分野のフィールド関係科目が共通科目でいくつか開講されているので、それらを受講するように指導したり、大学や県立及び市町村立博物館が実施している自然科学関係のフィールドワークを中心とする公開講座にも積極的に参加するよう推奨する。
第6節 図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程
【現 状】
① 設置経過、理念・目的
本学の図書館司書課程(図書館法により規定された、図書館で働く専門職員に必要な資格を修得させる課程)及び学校図書館司書教諭課程(学校図書館法により規定された、学校図書館の専門的職務を掌る教諭に必要な資格を修得させる課程)は、1995(平成7)年、本学短期大学部国文科に設置された。1996(平成8)年には短期大学部の廃止に伴い文学部国文学科に移設され、さらに2001(平成13)年からは文学部の改組により、総合文化学部日本文化学科に設置されている。
図書館司書課程は1996(平成8)年8月の図書館法施行規則の改正省令により1997(平成9)年度から、また学校図書館司書教諭課程は1997(平成9)年6月の学校図書館法の改正及び1998(平成10)年3月の学校図書館司書教諭講習の改正省令により1999(平成11)年度から、それぞれ新しいカリキュラムに移行している。
図書館司書課程の理念・目的は、情報社会への時代変化に的確に対応できる新たな知識と技能を身につけ、利用者の学習ニーズに適切に対応することのできる図書館の専門的職員を養成すること、また学校図書館司書教諭課程では、社会変化に対応した学校の新しい教育活動を支えることができる見識や能力を備えた教員を養成することにより、「沖縄」という地域社会における公共図書館や学校図書館などの図書館界全体の充実・発展に貢献することである。
なお、両課程ともに全学部学科の学生が履修することができる。
② 教育課程
図書館司書課程は「図書館法施行規則」に、また学校図書館司書教諭課程は「学校図書館司書教諭講習規定」に則り編成され、それぞれ文部省の審査を経て認可されたものである。
両課程の特徴は、前項の目的を実現するために、図書館司書資格科目では開設科目、開講期、単位数、履修年次を、また学校図書館司書教諭資格科目でも開講期や履修年次を、次のように設定していることである。
図書館法施行規則 |
本 学 課 程 |
群 |
科 目 |
単位 |
本 学 課 程 |
単位 |
年次 |
備 考 |
甲
群
・
必
修 |
生涯学習概論
図書館概論
図書館経営論
図書館サービス論
情報サービス概説
レファレンスサービス演習
情報検索演習
図書館資料論
専門資料論
資料組織概説
資料組織演習
児童サービス論 |
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
|
生涯学習概論
図書館概論
図書館経営論
図書館サービス論
情報サービス概説
レファレンスサービス演習
情報検索演習
図書館資料論
専門資料論
資料組織概説Ⅰ(分類)
資料組織概説Ⅱ(目録)
資料組織演習Ⅰ(分類)
資料組織演習Ⅱ(目録)
児童サービス論 |
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2 |
2
1
2
1
2
3
3
1
2
2
2
3
3
2 |
前・後期開講
前・後期開講
前・後期開講
前・後期開講 |
乙
群
・
選
択 |
図書及び図書館史
資料特論
情報機器論
図書館特論
コミュニケーション論 |
1
1
1
1
1 |
図書及び図書館史
資料特論
情報機器論
図書館特論 |
2
1
2
2 |
1
2
3
3 |
開講せず |
|
(注)1.開講科目: |
図書館の資料を整理する上で基本となる「分類・目録」は、それぞれ分離・独立させ各科目として開講している。 |
| 2.
単 位 数: |
a) |
選択科目のうち、図書館を取りまく社会環境の変化や、図書館の現状把握のために重要な科目は2単位としている。 |
| b) |
演習科目は1単位の設定だが、開講回数は全15週(2単位科目と同様の設定)としている。 |
| 3.履修年次: |
a) |
全科目間の履修順序は、概論から各論への順序とする。 |
| b) |
演習科目がある場合は、概論・概説科目で内容を把握してから履修する。 |
| 4.開 講 期 : |
演習科目は、徹底した少人数教育を展開させるため、毎年度前期・後期にそれぞれ開講している。 |
| 5.そ の 他 : |
「図書及び図書館史」科目で、沖縄の図書館の歴史を取り上げ、また「資料特論」科目では沖縄に関する郷土・行政資料にも触れることで、科目内容に地域社会との関連性を持たせている。 |
学校図書館司書教諭講習規定 |
本 学 課 程 |
| 群 |
科 目 |
単位 |
本 学 課 程 |
単位 |
年 |
備 考 |
必
修 |
学校経営と学校図書館 |
2 |
学校経営と学校図書館 |
2 |
3 |
|
| 学校図書館メディアの構成 |
2 |
学校図書館メディアの構成 |
2 |
3 |
|
| 学習指導と学校図書館 |
2 |
学習指導と学校図書館 |
2 |
3 |
|
| 読書と豊かな人間性 |
2 |
読書と豊かな人間性 |
2 |
3 |
|
| 情報メディアの活用 |
2 |
情報メディアの活用 |
2 |
3 |
前後期開講 |
| (注)1.履修年次: |
1年次から教職課程の履修をはじめ、教員免許の取得がほぼ確定する3年次から本課程は履修する。 |
| 2.開 講 期: |
演習科目は、徹底した少人数教育を展開させるため、毎年度前期・後期にそれぞれ開講している。 |
③ 教育方法・履修指導
両課程の教育方法の特徴は、社会変化に伴う新しい理念・目的をふまえ、各種図書館関係の理論と実践をどのように結びつければ、より良い図書館サービスを展開させることができるかを考え、実行できる能力を修得させることである。そのため兼任講師には県内の様々な図書館現場において、経験に基づいた知識と技能を蓄積した人材を任用している。
また、前項でも触れたように演習科目は、少人数教育をおこなうことにより、実務的能力を具体的に身につけさせるように編成している。
さらに、開設学科である日本文化学科の「人文情報コース」には、図書館情報学ゼミが開設されており、図書館司書資格とは別に、3・4年次の専門課程で公共図書館や学校図書館に関する諸問題を取り上げて研究することができる。
なお、両課程の履修希望者に対する全学的な履修指導は、毎年新入生を主な対象として、年度初めにおこなっている。オリエンテーションの内容は、開設科目間の関係や履修順序について『履修ガイド』に基づき全体的な説明をおこない、その後、学生からの個別的な質問を受け付け、相談に応じている。
④ 成果・実績
図書館司書資格は毎年約100名の本学学生が、また、学校図書館司書教諭資格は、文科省の委嘱を受けた夏期講習と合わせ、本学学生と学外受講生の約150~200名が資格を取得している。なかには、沖縄県内の各自治体の公務員試験に合格して、公立図書館や学校図書館に配属されている者や、臨時職員として県内各地の各種図書館現場で実務に携わっている者もいる。
本学に図書館司書、学校図書館司書教諭課程が設置されて10年だが、着実に沖縄という地域社会の図書館界を支える若い人材を輩出している。
【点検・評価】
本課程の理念・目的は適切であり、着実に成果・実績に結びついてきている。
教育課程は、図書館司書課程の選択科目のうち「コミュニケーション論」が開講されていない点を除いて適切である。
教育方法は、時代の要請する図書館の専門的職員の養成を目指し、新しい知識と少人数演習による技能を修得できる科目内容は成果を上げている。
履修指導は適切におこなわれているが、両課程が全学部学科に開放されているため、関係科目の時間割が、各学科の必修科目や他の資格科目と重複する場合がある。
図書館司書課程の必修科目のうち、「図書館概論」「図書館サービス論」「図書館資料論」の3科目は、日本文化学科の提供科目として卒業単位に含まれるため、受講生の中には、必ずしも図書館司書資格を修得しない者がおり受講意識・態度に格差が生じて、講義運営に支障をきたす場合がある。
両課程の教育方法をより徹底させるため、より多くの学外兼任講師を任用したいが、沖縄県内で各種図書館関係の教育に携われる人材の不足から、大きな困難がある。
また、本課程の専任教員(2名)は、開設学科に所属し学科業務も担当するため、本来の図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程担当教員の職務が妨げられているという問題もある。
【改善・改革方策】
教育課程については、図書館司書課程の「コミュニケーション論」の開講を今後検討する。
教育方法では、各演習科目の受講者数が一定数以上の場合には、演習補助要員を配置して教育内容を徹底させる。
図書館司書課程科目の受講資格は、図書館司書資格の取得を希望する者のみとする。
本課程で図書館司書資格を取得した卒業生の中には、図書館学関係の大学院に進学する者も出ている。沖縄県内での新たな兼任講師の任用が、人材不足から困難な状況のため、本学卒業生による人材確保をめざす。
図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程の専任教員については、所属学科の業務分担を可能な限り軽減する。
第7節 国際交流
本学の国際交流は本学の理念・目的と密接に結びついており、校名の沖縄「国際」大学がそれを如実に示している。本学は、昭和47年、日本へ施政権が返還された際、旧沖縄大学と旧国際大学が統合し設立された大学であるが、沖縄という地域自体が1879年まで独立した王国で、独自の長い海外交流の歴史を持ち、日本の一県となった後も、アジア諸国、ミクロネシア諸島、南北アメリカ諸国に数多くの移民を送り出してきた。現在では沖縄県が国際交流を重点施策に据え、様々な事業を次々と推進している。つまり、国際交流は沖縄県全体の特色でもあり、本学のキャッチフレーズである「地域に根ざし世界に開かれた大学」や、明文化された本学の理念、「地域の自立と国際社会の発展」というのは、本学の設立趣意書が謳う「沖縄の私立大学」としては、当然すぎる理念として自他共に認められる本学の特色となっている。
本学の国際交流は、草創期の本学の基盤整備が一段落するのを待って徐々に開始された。まず昭和52年、最初の外国人留学生3名を受け入れ、その後の10年間で合計73名が入学した。昭和57年には留学生を対象とした日本語・日本文化科目群も開講された。本格的な取り組みが行われる契機となったのは、昭和62年7月、本学理事長・学長の諮問に応えて、「沖縄国際大学の国際化について」の答申が出されてからである。当時すでに国際化の機運は熟していた。先ず本学の教員110名の45.5%が国外大学における留学・研修者で占められ、外国語の教育と施設が充実し、4名の専任外国人教員がおり、また各学部には国際関係科目が多数開講されていた。これらの基盤の上に答申の具体化に向けて動きだした。
さて答申を受け、「一国・地域に一大学」、「互恵平等」、「大学間の全面交流」の理念のもとに、名目的ではなく実質的交流を行うことを確認し、協定校の開拓に着手した。その結果、台湾の東海大学(平成元年)、中国の廈門大学(平成2年)、韓国の韓南大学(平成3年)、タイのヨノック大学(平成4年)、アメリカのベイラー大学(平成5年)、イギリスのアルスター大学(平成7年)、中国の澳門大学(平成9年)の7大学と協定を締結し、締結の翌年からそれぞれ交換留学生の相互派遣が行われ、また本学からは各協定校へ海外語学・文化セミナー研修生も派遣されるようになった。そのうち、東海大学とヨノック大学と韓南大学からは研修生の受入れも行った。これら7大学のうち、廈門大学とベイラー大学は協定を終了しているが、他の5大学とは現在も協定関係を維持している。また、平成7年には国際交流センターが設置され、交流事業については、所長(委員の互選)、副所長、教務部長、学生部長、図書館長、学部選出委員各2名、その他数名を構成員とする全学的な委員会、即ち国際交流委員会が発足し、国際交流を推進する体制が出来上がった。また国際交流センターの交流事業とは別に、南島文化研究所も単独で、平成9年、韓国の全南大学校湖南文化研究所と、平成14年、中国の福建師範大学中琉関係研究所と、それぞれ学術交流協定を締結し、独自に共同研究の実施や合同シンポジウムの開催など、研究を中心とする学術交流を実践している。
ここで、国際交流センターを中心とした国際交流について、内容別に本学国際交流の現状とその点検・評価、さらに改善・改革について述べることにしたい。
【現 状】
① 正規留学生、特別聴講学生、外国人科目等履修生、短期語学文化研修生について
最初の留学生が入学してから約四半世紀後の今日、本学には大学院生7名を含む正規留学生41名、学部・大学院研究生2名、(協定校から派遣された)特別聴講学生9名、外国人科目等履修生25名の合計77名が在学している。学生数は10年程前まで100名前後で推移していたが、最近は逓減状態が続いている。これは沖縄県全体の傾向と呼応するもので、景気の回復を待つしかない。正規留学生の世話は、国際交流センター、各学部、学生部、日本語担当教員が、また特別聴講学生の世話は、受入れ学部である商経学部、総合文化学部(特に世話役教員)と国際交流センター及び日本語担当教員が、また科目等履修生の世話は、主として国際交流センターと日本語担当教員がそれぞれ行っている。因みに、本学は留学生の日本語教育と日本語教員資格取得のための課程を運営するため、日本文化学科と英米言語文化学科にそれぞれ1名、合計2名の専任教員を配属している。
本学は留学生を対象とした宿舎がなく、大学周辺の適当なアパートなどの斡旋にとどまっている。但し、特別聴講学生については、受入れ大学が本学の交換留学生のため特別な措置を講じていることから、本学でもアパートの斡旋、家具のレンタル、生活費の支援など、特別な世話をしている。特別聴講学生の9名という数は、東海大学、韓南大学、澳門大学からの各3名で、ヨノック大学とアルスター大学からは諸般の事情により平成13年以降学生が来なくなっている。正規留学生に対しては国際教育協会など学外団体から種々の奨学金が支給されているが、本学独自の奨学金として、学外奨学金を受給できなかった学生を含めた全ての正規留学生を対象に、その納付金の半額に達する金額を奨学金として給付している。さらに、科目等履修生に対しては、その履修料を邦人履修生とは別枠に設定し、格安なものにしている。
協定校のうち東海大学と韓南大学(それに以前はヨノック大学も)から、毎年7月(ヨノック大学は10月)に短期の語学文化研修生を受入れている。平成14年度は、東海大学からは14名、韓南大学からは13名がこの夏期プログラムに参加した。これまで参加した学生数は、東海大学からは平成2年の初回から数えて平成14年度までに合計173名が、ヨノック大学からは平成5年から平成13年度までに合計91名が、韓南大学からは平成12年から平成14年までに合計34名が本学の研修プログラムに参加し、総合計は298名となっている。これら外国人学生と本学の学生との交流も盛んで、交歓会、展示会、授業支援、沖縄案内などを通して、本学のキャンパスを彩る夏の風物詩となっている。
② 交換留学生、協定校海外語学・文化セミナー生の派遣について
平成15年度は、厳しい選抜試験を経て、国外の協定校4校へ合計11名(東海大学3名、韓南大学3名、澳門大学2名、アルスター大学3名)が派遣された。澳門大学にはインターン生1名も派遣されている。かつてはヨノック大学に、交換留学生の他に本学卒業生を日本語教師として1名派遣していた。平成13年度まではヨノック大学の2名を含め、この交換留学生の合計は13名であった。これらの交換留学生に対しては、事前準備に万全を期すことは勿論のこと、学生の経済的負担を軽減するため、学外機関からの奨学金の有無にかかわらず、一律に、年間納付金に相当する金額を奨学金として給付している。
本学の正規授業科目である短期海外語学・文化セミナーは、現在、ヨノック大学を除くすべての協定校で実施されている。平成14年度は、夏期に東海大学へ17名、韓南大学へ12名、アルスター大学へ10名を派遣した。因みに、これら送り出した研修生の総数は、東海大学は初年度の平成元年から平成14年までに合計159名、韓南大学は平成11年から平成14年まで合計59名、ヨノック大学は平成4年から平成13年まで合計139名、アルスター大学は平成7年から平成14年まで合計104名、澳門大学は平成11年から平成12年まで合計11名で、合計472名となっている。短期の語学・文化セミナーについては、ここ数年、受入れ・派遣共に参加人員がやや減少しつつあるが、この短期セミナーの費用はすべて学生の自己負担であり、景気の動向を反映しているかも知れない。
③ 協定校への研究員の派遣とその受入れについて
協定校との交流は、学生の交流ばかりでなく、教員の交流も行われている。派遣の方は、教員の中から希望者を募り、毎年3名を研究員として本人が希望する協定校へ一か月間派遣している。また受入れは、協定校のうちから毎年1校を順番で決定し、1名の教員を客員研究員として1ヶ月間招待している。この制度で派遣した研究員は平成14年度までに合計15名、受入れた研究員も同じく合計15名にのぼっている。
④ 協定校による合同国際学術セミナーの開催について
本学は協定校と協力して国際学術セミナーを開催してきた。特に韓国の韓南大学とは協定締結の翌年の平成4年、韓南大学が主催して「韓国と沖縄の民俗学術発表会」を主催したのを皮切りに、隔年毎に、本学と韓南が交互にセミナーを主催してきた。平成8年、本学の当番の際、本学は本学のすべての国外協定校と関係者に呼びかけ、2日間にまたがる大規模な「‘96国際平和学シンポジウム」を開催した。基調講演者のヨハン・ガルトゥング(元オスロ国際平和研究所所長)をはじめ、国内外の著名な平和学関係者、大田昌秀沖縄県知事ら多数が参加し、マスコミでも大きく取り上げられた。平成9年には、韓南大学と東海大学の協力を得て、再び本学において合同学術セミナー「家族の変容:ジェンダーの視点から」を開催し、平成13年にも、韓南大学、東海大学、ヨノック大学、澳門大学が協力して、「東アジアにおける日本語教育の現状と課題」が本学で開催された。また当然のことながら、各協定校で学術セミナー開催される場合は、招待に応じ、本学から発表者を派遣している。先に触れた研究所間の交流内容は省略する。
⑤ 国外研修員の派遣について
すでに述べたように、本学は協定校へ短期の研究を派遣しているが、それとは別に、1年という期間で、国外の大学や研究所へ毎年2名の研修員を派遣している。この制度は、昭和50年、派遣数1名をもってスタートした制度だが、昭和59年からは派遣の枠が2名となり、その後平成14年度までに合計41名の教員が国外へ派遣されている。
⑥ 外国人専任教員の存在について
国際交流が本格化した昭和62年に4名であった専任(当時は任期制)の外国人教員は、その後雇用条件が日本人教員と同一に改まり、平成15年5月現在、数も7名(アメリカ人3名、イギリス人、中国人、韓国人、タイ人各1名)に増えた。平成16年度に向けてさらに2名の外国人専任教員が加わる予定である。
【点検・評価】
本学の国際交流は、本学が地方の一私学であること、学生数も約5,000名に過ぎないことなどを考慮すれば、高い評価に値すると考えられる。特に、沖縄県にある8つの国公私大のうち、その計画性、多様性、継続性、実質性、社会性などから判断して1、2位にランクされることは疑いのないところである。ただ、タイのヨノック大学は先方の受入れ態勢の不備で中断し、イギリスのアルスター大学においても学内の事情で本学に留学生を派遣することが出来ず、本学の一方的派遣に深刻な影響を与えそうである。さらに、正規留学生の数の低迷と、本学が派遣している海外語学・文化セミナーの数と協定校からの受入れ人数の低迷も、心配の種となりつつある。また本学の留学生に対する奨学金の充実ぶりは特筆に価するが、宿舎はまだ未整備のままである。全県的な組織である沖縄地域留学生交流推進協会でもこの問題が取り上げられているが、推進母体となるべき沖縄県が緊縮財政を理由に実行に移す気配を見せてない。
【改善・改革方策】
ヨノック大学とは従来から協定終了の声があり、ここ2、3年以内に決定が下されるはずである。またそれに代わる協定校としてエジプトのカイロ大学が浮上し、平成15年度中の協定締結が見込まれている。アルスター大学に代わる措置として、年間30名以上の学生(平成15年度は35名)が休学して国外機関へ私費留学している実情に鑑み、平成16年度から、現在の交換派遣留学生制度に加えて、新たに「海外キャリア形成プログラム(仮称)」という、学生派遣のみを行う、派遣留学制度を発足させる計画である。留学先はアメリカをはじめ、イギリス、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなどが候補に上がっている。そのための奨学金として、納付金の半額に相当する額を留学生に給付する案も浮上している。また留学生の逓減傾向に歯止めをかけるため、日本語学校などに働きかけて外国人科目等履修生の獲得を図る一方で、学内における留学生教育をさらに充実させるよう、国際交流センターで集中的に検討する予定である。